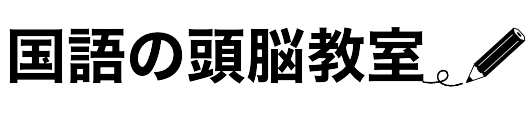私がこれまでに多くの中学受験生を見て来た。
「一番伸びた」と断言できるのは、決して最初から読書好きで成績上位だった子ではなかった。むしろ、国語が苦手で、模試でも時間が足りずに白紙を残すようなタイプだった。
だからこそ、彼が半年間で偏差値を15以上伸ばしたとき、周囲の誰もが驚いた。ここではその子の姿を紹介しながら、「国語で伸びる生徒」の特徴を語ってみたい。
初めは「とにかく読めない」生徒
その子を初めて教えたのは小学校5年生の冬だった。
模試の成績表には、算数や理科の数字が並んでいるのに、国語だけが極端に低い。記号問題は勘で答えることもあるらしく、正答率はほとんど偶然だった。文章題になると、本文を最後まで読み切れず、設問の意味も分からないまま時間切れになる。
本人に聞いてみると「国語って、答えがひとつじゃないから嫌いなんです」と言う。まさに国語嫌いの典型だった。
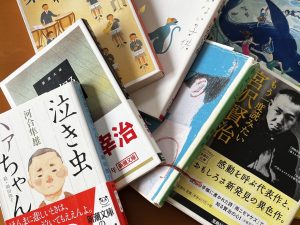
小さな変化を重ねることから始まった
最初にやったことは、文章を最後まで読むこと。
そのために、私は「設問を先に読む」方法を教えた。問題文の冒頭を読む前に、まず設問をチェックして「何を探すのか」を意識させる。たとえば「登場人物の気持ちを答えなさい」とあれば、その感情の変化に注意して読む。「筆者の意見をまとめよ」とあれば、逆接や接続詞に印をつけながら読む。
こうして読む目的をはっきりさせると、それまで漠然と文章を眺めていただけの彼が、少しずつ「文章を追いかける目」を持つようになった。
最初のうちは時間がかかり、1題解くだけでぐったりしていた。
しかし根気よく続けるうちに、「この言葉は逆の意味を表している」「ここがまとめの部分だ」と本人の口から出るようになった。その変化が見えたとき、私は「この子は必ず伸びる」と確信した。
「なぜ」を問い続ける姿勢
次に取り組んだのは答え合わせの仕方だ。
多くの生徒は、丸つけをして終わりにしてしまう。しかし彼には「なぜ間違えたのか」「正解は本文のどの部分にあるのか」を必ず口に出して説明させた。最初は面倒がっていたが、習慣になってくると「本文の三段落目に理由がありました」「選択肢のこの言葉が本文と違いました」と、自分から根拠を示せるようになった。
記述問題では、模範解答をそのまま写させるのではなく、自分の言葉で言い換える練習を繰り返した。
模範解答を読み上げ、「つまりどういうこと?」と聞き返す。すると彼は言葉に詰まりながらも、少しずつ因果関係を組み立てて説明できるようになった。この「自分の言葉で言い直す」訓練こそが、国語を伸ばす最大の秘訣だった。

語彙力と表現力の積み重ね
さらに大事だったのは語彙力だ。
読書量の少なかった彼は、比喩表現や四字熟語に弱く、すぐにつまずいてしまう。そこで、授業ごとに「今日の言葉」として三つの語句を選び、例文を作らせた。たとえば「一石二鳥」「安易」「矛盾」などを、その日の出来事と結びつけて短文にする。最初はぎこちなかったが、数か月経つと自然に使えるようになり、記述の文章にも厚みが出てきた。

模試での大逆転
5年生の終わり、初めて時間通りに模試を解き切った。
結果は偏差値40台後半。まだ十分ではなかったが、本人にとっては大きな自信となった。
そして6年生の夏、ある模試で国語が偏差値60を超えた。算数や理科と肩を並べ、総合判定が急に上がったのだ。本人の驚いた顔を今でも覚えている。「国語って、やればできるんですね」と照れくさそうに笑った。
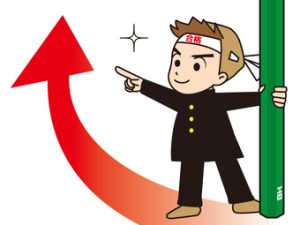
本番での強さ
入試本番でも、その成果は生きた。
制限時間の中で焦らずに本文を読み、設問ごとに根拠を探し、記述では「〜だから〜だ」と筋道を立てて答える。大きな白紙を出すこともなく、最後まで解き切る姿勢を貫いた。その結果、第一志望校に合格。合格発表の日、涙を流して喜ぶ彼と家族を見て、私は「国語は決して才能ではなく、方法で伸びる教科だ」と改めて実感した。
まとめ ― 伸びる生徒の共通点
この生徒の姿から分かるのは、国語が伸びる子には以下の特徴があるということだ。
- 設問を先に読んで目的を持って文章を読む
- 答え合わせで「なぜ」を問い続け、根拠を示す
- 模範解答を自分の言葉で言い換える
- 語彙力を少しずつ積み重ねる
- 時間配分を意識し、本番を想定した練習を繰り返す
才能や読書量よりも、こうした習慣と努力が国語の成績を決定づける。苦手だからと諦めず、正しい方法を続けられる子こそが、一番大きく伸びるのだ。